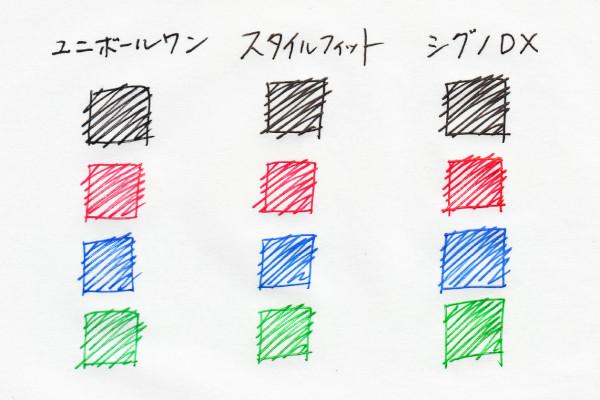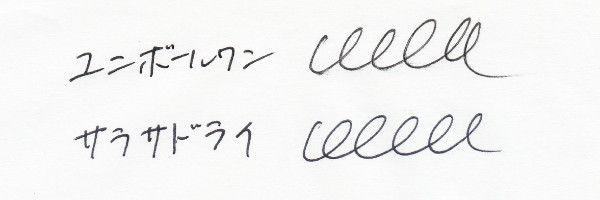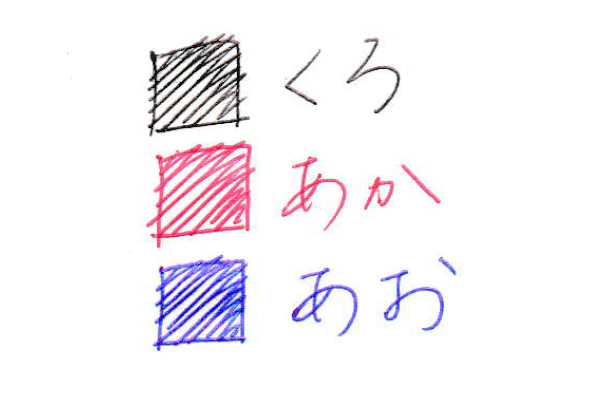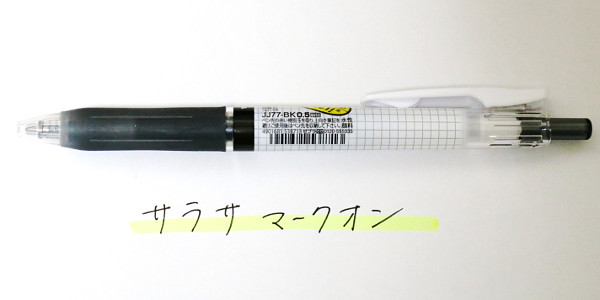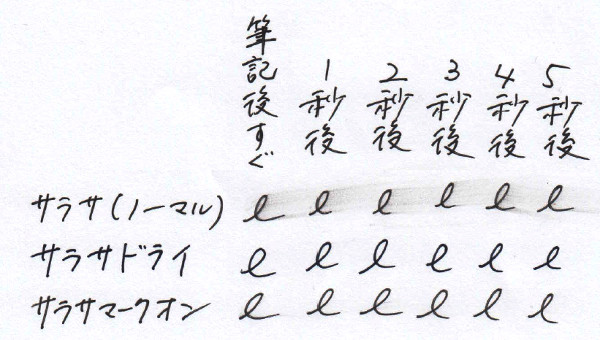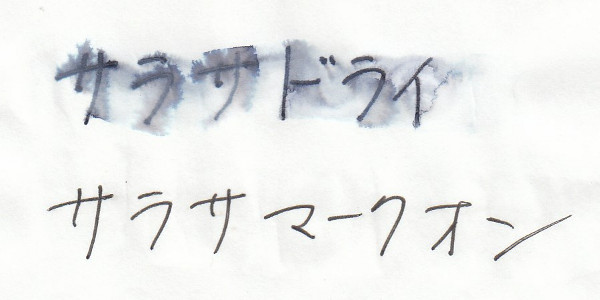SSL化を実施
- 2020/12/30 23:11
- タグ:雑記
本日、skygrass.net内の全ページをSSL化(https化)した。これにより、トップページのアドレスは「http://skygrass.net」から「https://skygrass.net/」に変更となった。なお、「http://~」のURLにアクセスがあった場合は自動的に「https://~」に転送されるように、.htaccessを使用して設定している。
今回SSL化したのは、セキュリティを考慮して……といったたいそうな理由からではなく、ブラウザ上で「接続は保護されていません」というような注意表示が出るのが何となく嫌だったからだ。お粗末な理由かもしれないが、とは言え、セキュリティが強化されるのは事実なので、けっして悪い変更ではないはずだ。
一部、「http://~」のURL(絶対パス)で画像を読み込んでいるため、引き続き注意表示の出るページがあるが、アクセスの多そうなページを優先して、おいおい修正していけたらと考えている。